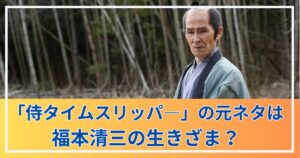Netflixで配信が始まった映画『新幹線大爆破』が、SNSや映画ファンの間でちょっとした論争を巻き起こしています。
「キアヌ・リーブス主演のハリウッド映画『スピード』のパクリなのでは?」という声が、一部の視聴者から上がったのです。
その理由は明白です。爆弾を仕掛けられた乗り物が舞台で、一定の速度を下回ると爆発するという設定。さらに、緊迫感ある交渉劇と、乗客を救おうとする主人公たちの奮闘。これらの要素は、確かに『スピード』(1994年公開)と非常によく似ています。
そもそも『新幹線大爆破』とは何か?
1975年に日本で公開された『新幹線大爆破』は、実在する新幹線を舞台に、爆弾テロという極限状況を描いた社会派サスペンスです。
「時速80km以下になると爆発する爆弾が列車に仕掛けられている」という緊張感あふれる設定で、日本映画としては異例のスケールとリアリズムを持った作品でした。
監督は佐藤純彌。出演には高倉健、宇津井健、丹波哲郎といった昭和の名優たちが顔を揃え、単なる娯楽ではなく、社会性を帯びた映画として評価されてきました。
Netflix版は「パクリ」では無く、オリジナルの現代的リブート
Netflixで新たに公開された『新幹線大爆破』(2024年配信開始)は、1975年版のオリジナルを基にしながら、現代的な演出と国際的キャストを用いてリメイクされた作品です。
もうお分かりですね。
Netflixで新たに公開されたこの『新幹線大爆破』は、1975年に日本で制作された同名映画のリブート作品なのです。
つまり、『スピード』よりもはるかに早い時代にオリジナルが存在していたという驚きの真相がありました。
◉ 主なキャスト(Netflix版)
- 草彅剛(高市和也)2003年4月にJR東日本に入社し、盛岡新幹線運輸区所属。車内の混乱の回避や、立案された作戦には積極的に協力し、爆発を回避しようと奔走した。車内のポスターを見て東京駅で東北新幹線の線路を東海道新幹線へと繋ぎ、はやぶさを鹿児島中央駅まで走らせようと考えた。
- のん(松本千花)2018年4月にJR東日本に入社し、盛岡新幹線運輸区所属。指令所から爆弾に関する電話を受けた際には訓練だと勘違いした。盛岡駅付近で、はやぶさ・こまち27号(3027B)との上り列車の逆線運転を行った際に笠置から時速を120kmから100km際まで落とせと言われ、取り乱すこともあった。
- 斎藤工(笠置雄)JR東日本新幹線総合指令所の総括指令長。警察や政府との連携、作戦の立案などを行った。
- 要潤(等々力満)はやぶさ60号(5060B)の9号車(グリーン車)に乗っていた起業家YouTuber。本名はサトウヨシヒロ。島根県出身。青森県には、自身の本である「ニートで大富豪」の講演会や県議との会食のために訪れていた。政府よりも先に解除料についての行動を起こし、自身のファンドでクラウドファンディングを行った。加賀美らが気になり、立ち上がった際の成り行きで60号へ向かい、そのまま取り残された。
- ゆりやんレトリィバァ(車内アナウンス声 )救出車両において車内アナウンスを行う。
Netflix版では、現代のセキュリティ体制や交通インフラの描写も取り入れ、オリジナルの緊張感をそのままに、テンポの速いアクションと心理ドラマが融合した仕上がりとなっています。
なぜ「スピード」のパクリと誤解されたのか?
『スピード』は1994年に公開され、バスに爆弾が仕掛けられ、時速50マイル(約80km)を下回ると爆発するというプロットで世界的ヒットを記録しました。
このアイディアが斬新に思われがちですが、実は『新幹線大爆破』の設定とほぼ同じなのです。
そのため、Netflix版『新幹線大爆破』を初めて見る世代にとっては、『スピード』を思い出すのも無理はありません。しかし実際には、時系列上『スピード』の方が『新幹線大爆破』の“後”に公開されており、むしろ『スピード』こそが、日本映画に影響を受けた可能性があると言えるのです。
映画の歴史を逆照射するNetflixの力
Netflixでの配信は、過去の名作を現代に蘇らせる装置でもあります。
今回の『新幹線大爆破』のように、再解釈や誤解から始まった話題が、結果として日本映画のオリジナリティを再評価する流れを生んでいるのは、非常に興味深い現象です。
「誰が誰をパクったのか」という表面的な議論だけでなく、「どのように物語や演出が時代と共にリメイクされ、世界とつながっていくのか」に目を向けることが、映画ファンにとってはより重要ではないでしょうか。
結論:これは“パクリ”ではなく、“リバイバル”である
Netflix版『新幹線大爆破』は、決して『スピード』の模倣ではありません。
むしろ、日本が先に生み出していたアイディアを、現代に合わせて再構築したリバイバル作品なのです。
この誤解こそが、日本映画の先見性と、世界映画史における存在感を再認識させてくれます。
今後も、こうした“逆輸入”型のリブート作品が、国境を超えて再評価されることを期待したいところです。